トップページ > Spirit of "Mikokoro" > 3月1日高等科卒業式 聖心の教えを受け継ぐ 渉猟をたどって
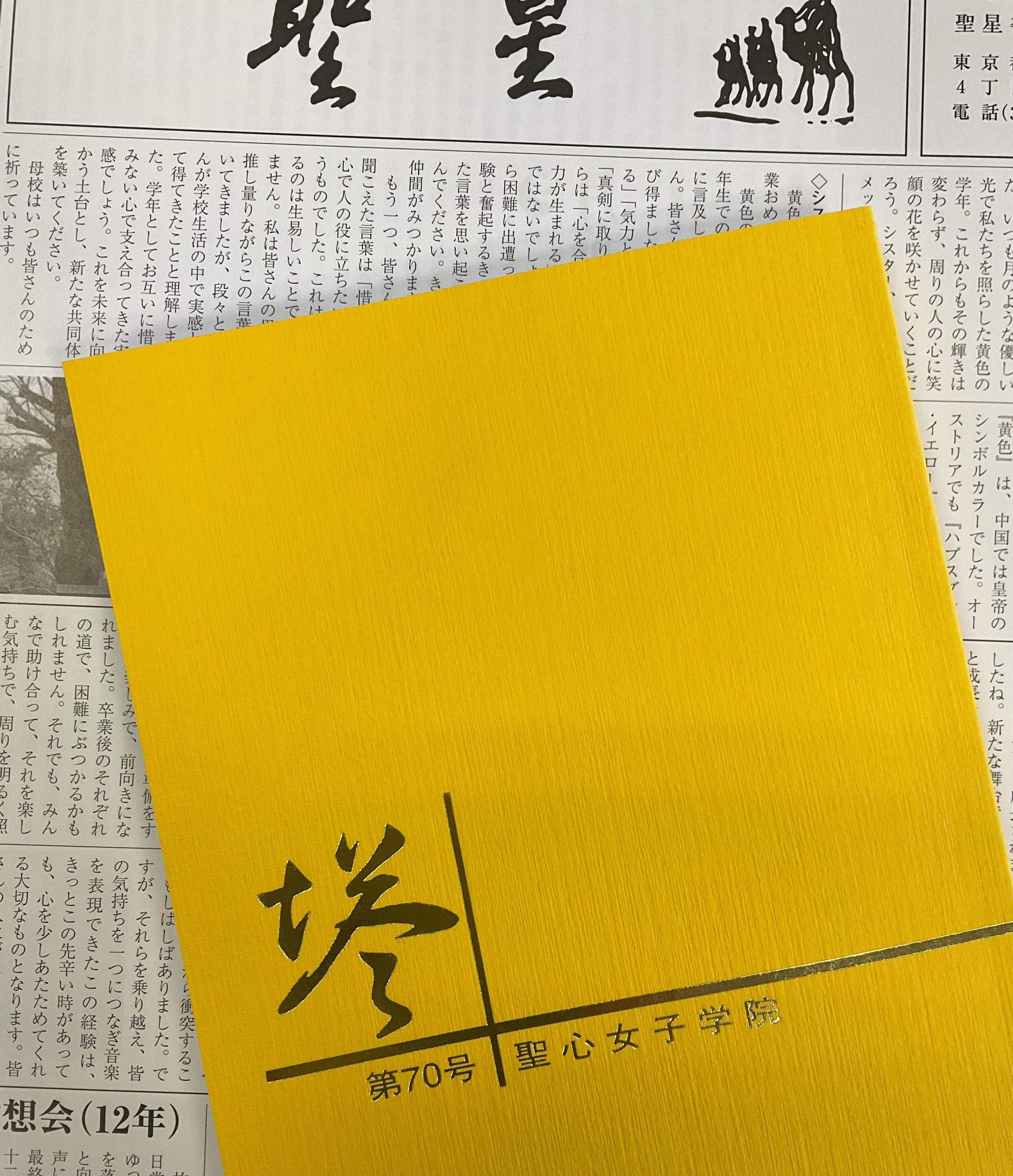
3月1日に高等科110回生卒業式を行いました。学年カラーでは黄色の学年でした。この学年らしい、春の陽射しの明るい天候に恵まれ、晴れやかな日となりました。卒業生たちのこれからの恵みを祈り、保護者の皆様のこれまでのご理解と支えに感謝いたします。画像は校内新聞と校内誌です。
~~***~~
黄色の学年の皆さん、ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様にもお祝い申し上げます。
二月の終わりの寒さを越えて、明るい陽射しの中、皆さんの卒業という喜ばしい日を迎えました。黄色の明るさや華やかさにふさわしい旅立ちの時です。
皆さんの学年は、学年としてのまとまりとパワーを11年・12年と学校行事を通して実感することができたという恵まれた経験をしてきました。これは言うまでもないことでしょう。皆さんは心の中で、お互いにそうそう、と納得してくださると思います。コロナ禍によって発揮する機会を眠らせてきた力を、一度底辺に下ってから一気に開花させてきました。それは、皆さんにとって、目を開かせられる経験だったでしょう。私たちはこういうことができる力をもっていたんだ、という実感を得る機会だったでしょう。とても大事なことでした。皆さんは恵まれた学年だと思います。そして、このことを学校生活の思い出に終わらせてほしくないと私は願っています。
昨年の秋に始めた皆さんとの面談で、多くの方から聖心生として大切なこととして、「人のために惜しみなく働く」という言葉が聞かれました。「惜しみない心」 generosity は、確かに聖心の私たちが創立者から受け継ぐ大切な価値です。皆さんがこれを大切にしてくださることはとてもうれしいことです。しかし、この大切な、聖心の究極の言葉を何人もの方から聞いて、だんだんと私は不思議な気持ちになりました。と言うのも、「人のために惜しみなく働く」と言うことは生やさしいことではないからです。それをどうして、このように何人もが、それも気負わずに口にするのだろう。真剣に考えて言っているのだろうか。しかし、この疑問は全員の面談を終える頃に解けました。つまり、皆さんは学校生活の中で、誰かの惜しみない力に助けられたり、誰かが全力で人のために働いている姿に接したり、お互いに誰かのために一生懸命に尽くしたりなどの活動をいくつも体験してきた実感があるのだろう、だから、口先でなく、実感のこもったこととして、「人のために惜しみなく働く」ということを言うことができるのだろう、こういう理解です。当たっているでしょうか。
皆さんは聖心に入学し、友人と出会い、黄色の学年としての意味深い体験を通して、聖心の価値を身につけ、今日卒業していきます。聖心との出会いは、皆さんに大きなものをもたらしました。
今、次の段階へと歩みを進められる皆さんに、出会いを新たに拓いていただきたいと思い、もう少し話を続けさせていただきます。
私に「渉猟」という言葉を教えてくださった方があります。渉猟という言葉はあまり使わない表現かもしれません。平和のために交渉するというときの「渉」の字と、動物を狩るという意味の狩猟の「猟」の字を書きます。その意味は、山の中を歩いて渡ったり、あちらこちら広く何かを漁り歩いたりすることですが、そこから、多くの書物を読み漁ることの意味としても使われます。私に「渉猟」を教えてくださった方は研究者で、聖心の教育や女子教育の歴史について知りたいことがあって、遠くから私を訪ねてこられたのです。そのときに、私から差し上げられる情報は残念ながらわずかでしたが、「渉猟」という点で意気投合しました。つまり、知りたいことがあるときにはとにかく渉猟する、可能性がありそうなあらゆる文献や資料を探す、漁り回る、ということです。その方は渉猟の一端として私を訪ねてこられ、私はその方の話を聞いて、渉猟ということが深く共感できました。と言うのも、何かをわかりたい、皆さんに何かを伝えたい、と言うときに、私も渉猟を実践していたからです。渉猟しても、役立つものはわずかかもしれない。でも、知りたいこと、真実やほんものを求めて探し続ける。それは大切な作業で、苦労は多くても楽しいことでもあるのです。
今回もこの卒業式で皆さんに何を伝えるべきか考えながら、図書館に行って書棚の間を歩き回りました。インターネットや新しく出現したチャットGPTも有効なツールです。しかし、本には受け継がれてきた価値があります。その中で、私は今回、真に渉猟という言葉にふさわしいと感じる人物に気づきました。今日、皆さんにぜひ伝え、渡したいのは須賀敦子という聖心の卒業生です。須賀敦子は小林聖心で育たれましたが、私たちのこの聖心女子学院にも一時在学され、聖心女子大学の第一回生です。そして、フランス、イタリアへの留学を経て、上智大学で教壇に立ちながら、イタリア文学の翻訳やエッセイを著す仕事をしました。1998年に亡くなられましたが、今でも彼女の文章は人気があります。私はこの方に学生の時にお会いするという幸運なチャンスがありました。そして、この方は私の人生の中で、聖心の教育の価値に気づかせてくださった大事なポイントに立つ方だと改めて感じています。
その時私は聖心女子大学を卒業してから、別の大学の大学院で勉学を続けていて、友人たちと英語訳のダンテの「神曲」を読んでいました。「神曲」というのは、十三世紀のイタリアで書かれた長い詩で、亡くなった恋人を求めて詩人が地獄に下り、煉獄を通って天国へと旅をするものです。西洋文学の古典です。それを読み始めて、面白さに深く感じ入っていました。ちょうど須賀先生が聖心女子大学でこの「神曲」の講義をされると知り、私は聖心女子大学での恩師にお願いして、聴講に通わせていただきました。その時、須賀先生は、毎回ご自分が聖心大に行く時に、通り道だからついでに一緒に行きましょう、と言ってご自分の運転する車に私を乗せてくださったのでした。一介の学生を気さくに扱ってくださるお人柄で、車中で色々なお話を伺いました。そして、学者としての知識・教養もさることながら、キリスト者としての深い信仰をもち、多様な人と関わりながら、しっかりと地に足をつけて生きている方だと感じました。聖心の卒業生とはこういう人なのだと強く感じたのでした。聖心の外に出て、広い世界を楽しんでいるつもりであった私は、このとき聖心のほんものに出会ってしまったのです。それは須賀先生が著作家として有名になって行かれる少し前のことで、私は先生が何者であるかを知らずに出会っていたのです。後に文章を読んで、その歩まれた人生の豊かさを深く理解しました。そして、この出会いは私が聖心に帰ってくるきっかけの一つとなりました。
須賀敦子は本に関する文章を数多く書いています。「塩1トンの読書」や「本に読まれて」など、タイトルに本がつく作品もあります。彼女も渉猟された方だったと言えます。生きるということを知るために、文学の世界を渉猟されています。そして、本を通して、生きるということを私たちに伝えています。皆さんもいつか須賀敦子の文章を読み、須賀敦子に出会ってほしいと思います。
須賀敦子を知るある方が、とても困った状況になったときに、須賀さんは遠くからとにかく駆けつけてきてくれた、何かできることはないかと思ってと言って来てくれた、と教えてくださったことがあります。読むことと生きることが緊密につながっていて、そこに人のために役に立つということを実現している方でした。
須賀敦子が生きた聖心の教えを私が受け取り、また皆さんに受け渡します。自分のスタイルで、現代の状況にあったやり方で、聖心生としてほんものの生き方を貫いてください。須賀敦子は「じぶんのあたまで、余裕をもってものを考えることの大切さを思う。五十年まえ、私たちはそう考えて出発したはずだったのに」という言葉を残しています。自分の頭でものを考える、というのは聖心の教えです。戦後50年の時にこれを書いています。「自分でしっかり考えているか」、今の世界にあって、私たちは本気でこのことを考えなければならないでしょう。既成の枠組みはゆり動かされています。情報はあふれています。何が正しいことなのか一人ひとり考えなければ、流されていきます。人ごとでは確かに生きられません。自分ごととして考えなければなりません。そして、自分で生き、人とつながり、ほんものを確かめることです。
須賀敦子の渉猟の向こうには、イスラエルの野を渉猟するイエスの姿があります。イエスは、苦しんでいる人、悲しんでいる人、貧しい人、病んでいる人、疎外されている人、出会う人すべてに神の愛を伝えるために、人を漁る(すなどる)ために渉猟しています。
今日、聖心女子学院を卒業して広い世界に出ていく皆さんは人生の渉猟の旅を始めます。これからたくさんの人に出会います。そこでよい出会いに恵まれて、生きることを学び、前に進む力をいただくように祈ります。そして、皆さんに出会った人が、皆さんを通して、損得で動かされない、共に生きる、つながる力や生きる力、何か特別によいものを皆さんの中に感じ取り、そこに生きた聖心の教えを見つけてくださるようにとも祈ります。母校もいつも皆さんのために祈っています。
これを皆さんへの今日のお祝いの言葉といたします。